【障害者雇用】企業には雇用における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務がある!実態は?
2022/07/25
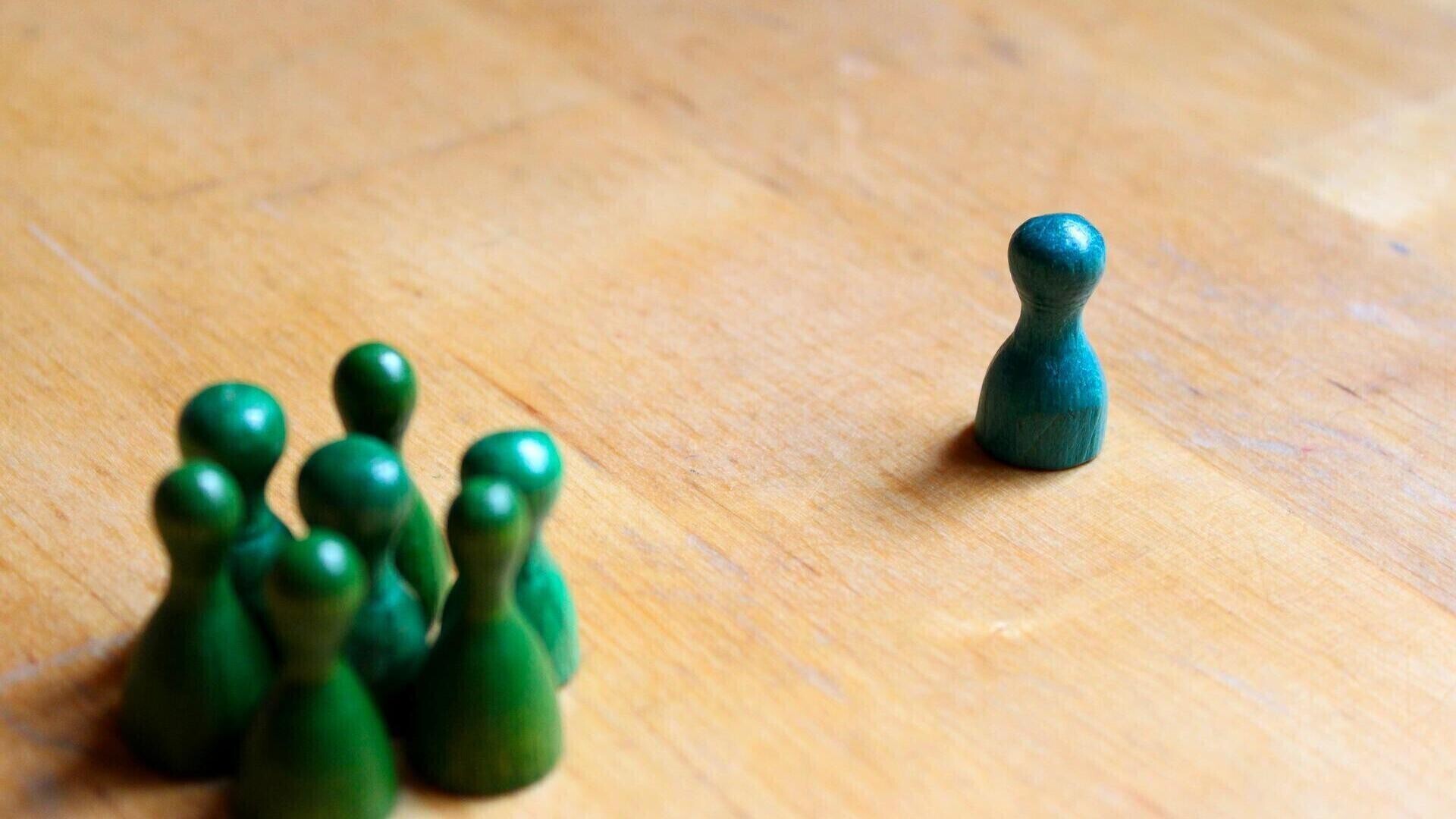
厚生労働省は2022年6月24日、令和3年分の「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績」を公開しました。
この実績は、都道府県労働局やハローワークにおける障害者の差別・配慮等に関する相談をまとめたものです。
障害者雇用に関する実態はどうなっているのでしょうか。
相談件数はどれくらい?
公開された相談実績を見ると、ハローワークに寄せられた障害者差別・合理的配慮に関する相談は244件です。多いように思いますが、これでも前年度より0.8%減少しているそうです。
一方で、労働局長による紛争解決の援助申し立て受理件数は2件のみで、前年度の12件から大きく減少しています。
この、『労働局長における紛争解決の援助申し立て』というのは、労働者と事業主との間にトラブルが発生した際、
公正・中立な立場から当事者双方の意見を十分に聴取し、双方の意見を尊重しつつ、問題解決に必要な具体策の提示をして、
トラブルの解決を図る制度で、紛争の当事者である男女労働者および事業主が援助を受けることが出来ます。
障害差別だけではなく、性別の差別や婚姻を理由とする解雇などの紛争にも関与します。
また、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は前年度から5件増加の10件になっています。
障害者雇用促進法(以下「法」)では、すべての事業主に対して、「障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止」(法第34条及び第35条)、「障害者に対する合理的配慮の提供義務」(法第36条の2及び第36条の3)、「障害者からの相談に対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」(法第36条の4及び第74条の4)を規定しています。 事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導・勧告(法第36条の6)により是正を図っています。
引用:PSRNETWORK
上記引用のように、差別することは許されることではないのですが、0にはなっていないのが現状です。
厚生労働省は、雇用分野における障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度の施行状況を踏まえ、さらに制度の周知に努めるとしています。
差別の禁止及び具体的配慮の提供義務ってなに?
障害者への労働上の差別とは、募集・採用の機会の際に障害があることを理由として募集・採用を拒否することや、
待遇の面で賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないことなどがあります。
また、障害を持つ方の雇用環境にはそれぞれ合理的配慮が必要となります。企業側は、これらを提供する義務があります。
募集の問題用紙を点字にしたり、音訳、拡大読書機を利用して試験を受けてもらうことも配慮にあたりますし、入社してからも車椅子の対応をしたり、手話通訳者や要約筆記者を配置する必要があることもあります。
対応事例はどんなもの?
ハローワークへの相談としては、「音や匂いに敏感という障害特性のため、在宅勤務等による静かな環境での就業を求めたのだが、配慮が受けられない」などといった相談があります。
他には、障害をオープンにせず仕事をしていた者が同僚からの暴言等に耐えられず、実は障害を持っているとオープンにしたら、賃金を下げられたといった事例もあります。
これらは、ハローワークから事業所へ助言が行われ、解決が図られています。
まとめ
障害者雇用は国が推進する雇用のあり方であり、差別はいけませんし、合理的配慮も必要です。
残念ながら差別はまだ残っていますが、減少してきています。
障害者雇用の改善は早急に求められています。すべての人たちが安心して働ける社会になると良いですね。




